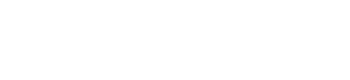永禄年間(1558頃)以来、製鉄法と共に布教されてきたキリスト教は、永禄、慶長年間頃には大籠、狼河原、馬籠等この地一帯に広まり、数多くの信者が製鉄や鍬作りに従事していた。
元和6年(1620)仙台で弾圧があってから、フランシスコ・バラヤス(日本名=孫右衛門)神父の教えにより、洞窟等を造り、信仰を続けていた。この大柄沢キリシタン洞窟もその一つであり、バラヤス孫右エ門神父の時に、この地方の信者のミサをあげるために造られた洞窟と思われる。
寛永16年(1639)バラヤス孫右エ門神父は仙台で捕えられ、江戸で処刑されてからは、この洞窟もミサは行われず、その後信者の移動と共に、あき洞窟となり、350年間人に知られず、今日に至っている。

昭和48年8月発見されたこの洞窟は、大籠教会から西へ1500m山奥で、東向きの斜面を利用して造られ、水平の水成岩層を堀抜いて造られている。
入り口付近で、高さ 1.3m、底辺1m、奥行10mの岩窟である。350年歳月を経ているが、奥の祭壇と思われる二段も、岩壁に掘られた。直径3cmの灯火用と思われる穴の中に、長さ3cmのくぎ状の金属も原形をそのまま残されている貴重な遺跡である。