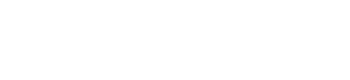当時この登米市、ことに東和地区は山地で蝦夷の住みかであったのかも知れない。
光仁天皇の後を受けた桓武天皇は、天応元年(781)に即位した。僧侶たちの政治干渉を避けるために、宝暦13年(794)に都を奈良から平安京に遷移した。これと同時に蝦夷征伐にも多大の努力をはらった。しかしさらに続いて反乱が起こった。特に平泉の西の達谷の岩屋を根拠地にしていた大嶽丸が中心となり、6人の家来を持ち多くの手下を従えて勢力を振るい、朝廷の指示にも従わなかった。征夷軍は造柵・新田柵等で固め、本郡の中津山に置かれた中山柵、桃生柵、牡鹿柵と一線が引かれて強力な防御線ができていたが、東和はその外に位置していて、監視され注意の地域であった。後には深い北上山地が続き、追われれば山に潜み、帰れば出る。山でも里でも生活のできるといった変幻自在の蝦夷たちであったので官軍も手を焼いたものであった。
坂上田村麻呂が征夷大将軍に命ぜられたのが、延暦16年(797)であった。東北に下った田村麻呂は、単に東夷征伐だけでなく、東北の開発にも力を尽くした。諸国から9千人の人民を栗原郡伊治(これはる)城に移して農業や養蚕をなさしめたと伝えられている。帰順した蝦夷たちにも土地を与えて生活の道を授けたので、帰順する者も相当に多かったようである。しかし生活が安定して永くこの地に住みついている蝦夷にとって不満があり、その後も何度も反乱を起こしている。
延暦20年(801)田村麻呂は陸奥国に下り伊治城からさらに北上して胆沢(いさわ)城を築いて、多賀城から鎮守府を移した。この工事中に帰順する者も非常に多かった。東北の人民蝦夷たちからの信頼が厚かったので、坂上田村麻呂にまつわる伝説が非常に多く、今に伝えられる伝説の地は何カ所もある。華足寺と馬ノ足もそのひとつ。(東和町史より抜粋)